こだままゆみです。

突然ですが、あなたは
アロマキャンドルを作るときに
香料をどれくらいの配分量を入れますか?
おそらく全体のワックスの量に対して
6%分を入れると習った人が多いと思います。
では、なぜ、
6%なのか?と考えたことはありますか?
今回の記事では、
なぜ、6%なのか?を答えのない答えを
探っていきます。
なぜ、6%なのか?
6%という数字はどこから出てきたのか?
こうして「問い」という思想の種を育てていくと
あなたのキャンドル作りにもっと深みが増しますよ。
アロマキャンドル香料6%
キャンドルスクールでのテキストや
キャンドルショップのフレグランスオイル商品詳細ページに
よく目にする数字があります。
「香料の推奨配合量:6%」
まるで、それが“正解”かのように
多くのレシピやハウツーサイトに
記載されています。
あなたは、
実際に香料6%の配合量で作ったことはありますか?
もし、作ったことがあるあなたへ。
香料6%の配合量で作ったアロマキャンドルは
どうでしたか?
・香りが強すぎた
・思ったより薄いかも?
・ちょうどいいと思った
さまざまな、感想を持ったと思います。
ちなみにわたしの場合は
6%という配合量は香りが強すぎて
頭痛が起きてしまいました。
わたしにとっては、
6%は化学テロでした。
人によって香りの適性濃度は違う
わたしの場合は、
ほんのり香るくらいが好きなので
100gのソイワックスに対して
5、6滴のフレグランスオイルを垂らすだけで
もう十分なのです。
灯しているときに、部屋の空気の流れによって
一瞬だけ強く香るあの瞬間が好きなのですよね〜。
あ、香った!!
というこの瞬間ですよ。
わかる人がいたら嬉しいです。
香りの濃度は、
強かったらいい、弱かったら好ましくない
といった判断は、
作る人使う人の主観的な感想です。
いつからか、
キャンドルが発する“香り”そのものよりも、
「香りに対してどう向き合うか」という姿勢も
持とうと意識が変わりました。
香料6%の数字はどこからきたのか?
化学的な観点から言うと
ソイワックスの分子とフレグランスオイルの分子が
よく混ざり合うのが6%から10%と言われています。
一般的に
香りも強すぎず、弱すぎず
燃焼にも影響しにくい
という点からきっとバランスの取れた比率なのかもしれません。
誰かが決めた”最適解”の数字。
それは、
効率的で失敗が少なく
多くの人にとって便利な指標です。
でも、
そこに思想があるか?と問われれば
少し違うかもしれません。
香料6%というルールは
・安心のための数字
・責任を取らないための数字
・考えることを省くための数字
にもなり得ます。
あなたにとっての最適解を
だから私は
こう問いかけてみたいのです。
「あなたにとっての“ちょうどいい香り”とは、なんですか?」
香りの感じ方は
人によって違います。
体調、気分、季節、時間帯。
あるいは、
その人の生い立ちや記憶などの
バックグランドにすら関係してくる。
それほどに繊細で、個人的で、
そして、変化しつづけるものなのに。
なぜ私たちは、
「配合量6%」を唯一の正解かのように
捉えてしまうのでしょうか?
思想で生きるというのは、
こうして日常のささやかな“当たり前”に
ふと立ち止まり
自分の感性で問い直してみることだと思うのです。
たとえそれが、
香料の配合量という小さな話であったとしても。
“正解”より、“深さ”を
“マニュアル”より、“あなたの感覚”を。
香料6%というルールのその先の
あなた自身の感性が、息づくようになると
あなたの作品に深みがまします。
これが、「思想の種」を持つことの始まりです。
もし、あなたが「この問いの感覚」に
少しでも心を動かされたのなら。
言葉と哲学で、
ソイキャンドルと向き合う3ヶ月間の講座を
ご用意しています。
毎週1通の問いかけから始まる
文通のようなやりとり。
“哲学するソイキャンドル”を、あなた自身の想いで灯してみませんか?
ソイキャンドルを哲学する3ヶ月メール講座はこちら▼
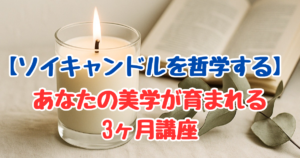



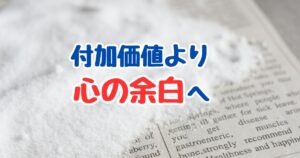
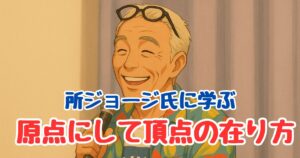
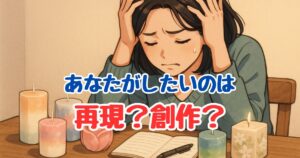
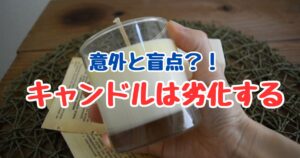


コメント